
化学による新たな価値創造で、
持続可能な社会の実現に貢献する
応用化学はあらゆる産業の
基礎となる分野です
化学技術は実社会では様々な分野で使用されており、医療関連や自動車、スマートフォンや飛行機まで、全て化学の力で成り立っています。「AIや情報ツールなどこれまで化学とは関係ない?」と思われていることも、実は応用化学の分野になります。
応用化学コースは、化学の言葉を使って様々なことを学び、研究・実践していくコースです。これまで学んできた「化学」をより社会に役立つように「応用」するためのコースが「応用化学コース」です。化学を学びながらその周辺の知識も学び、社会に出てすぐに必要とされている多くの知識を体系的に学んでいきます。
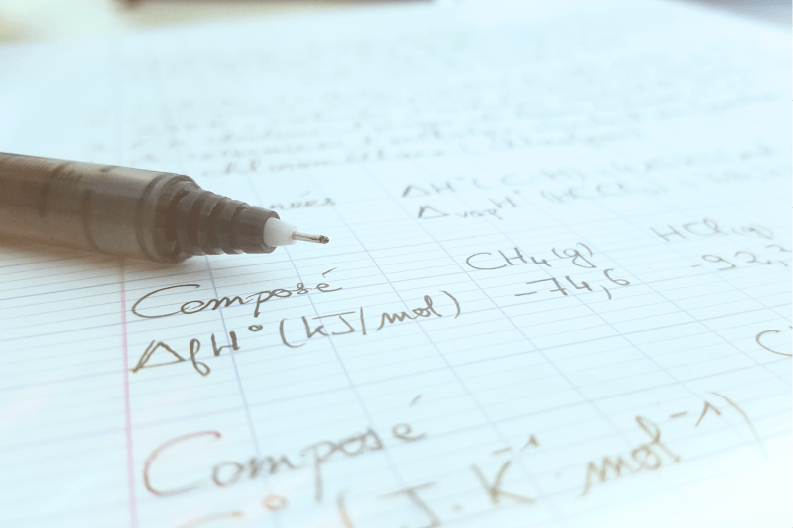

実践的な教育・カリキュラム
応用化学コースでは、化学の基礎から応用までを幅広く学ぶことができます。
応用化学コースの特徴は、化学の基礎知識と技術を系統的に習得できることに加えて、実験などの体験を通じた学びを特徴としたカリキュラムにあります。様々な実験を通じて、実験テクニックを身につけ、科学的な思考力や、問題発見能力を培います。また、実験方法を自分で考えて組み立てる「実験をデザインする」ことも学んでいきます。応用化学実験や卒業研究などの実践的な科目を通して、物質の取り扱いや分析・評価・設計・開発などの応用能力を養成します。
就職や大学院への進学、海外留学・インターンシップなどの国際的な活動にも対応できるように、英語力やコミュニケーション力も強化します。
pickup授業01
企業における課題と解決を学ぶ
社会の第一線で活躍している方々に講演していただき、化学分野における企業の特徴や社会から求められている人材像など、企業における課題解決の法論について学びます。
企業から提示された課題に対して、グループワークを通して、問題解決に取り組みむ実践的な講義です。
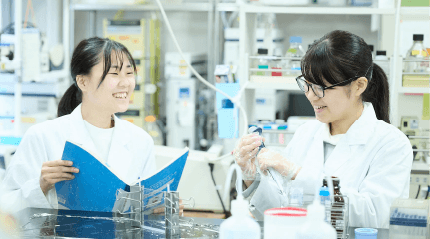
pickup授業02
機器分析ユニットプログラム
化学分野では様々な分析機器を用います。それらを一通り使いこなせるように各種の分析機器について基本的な測定原理を学んだうえ、対象試料の測定結果の解析に必要な知識を習得します。
高性能化、高機能化が進む分析機器に幅広く対応できる知識と能力をつけていきます。
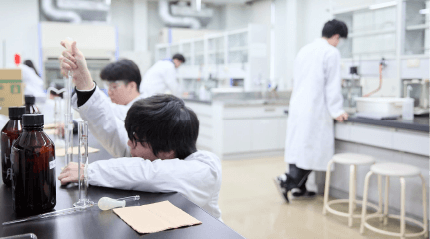
Student’s Voice
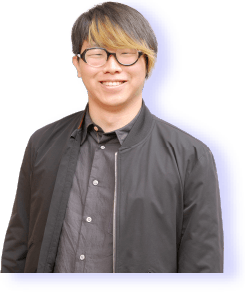
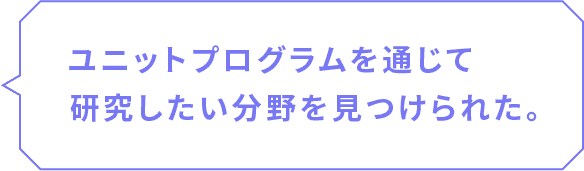
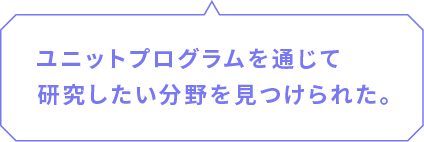
群馬大学大学院に進学
応用化学科 4年
群馬県立高崎北高等学校出身
岡田 望亜
座学と実習を一貫して学ぶ「ユニットプログラム」では、専門分野を深掘りすることで関心の幅が広がりました。実験を通じて特に面白いと感じた分野が有機化学。卒業研究では、「アズレン」という物質を用いた新規化合物の合成に挑戦しました。仮説通りに進む実験ばかりではありませんが、想定外の化学反応から突破口が見つかることも。大学院では研究の応用にも挑戦し、社会に貢献したいです。
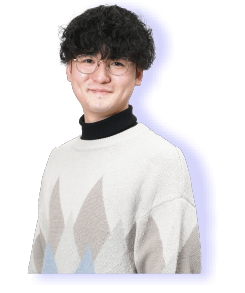
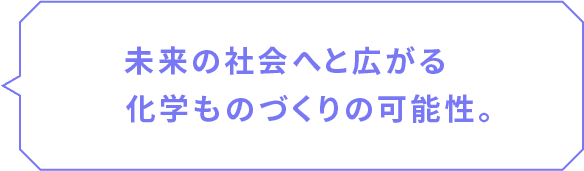
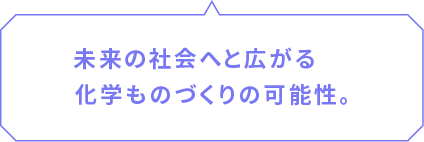
ニチレキ(株)に内定
応用化学科 4年
新潟県立柏崎総合高等学校出身
長崎 翔太
座学と実習を一貫して学ぶ「ユニットプログラム」では、専門分野を深掘りすることで関心の幅が広がりました。実験を通じて特に面白いと感じた分野が有機化学。卒業研究では、「アズレン」という物質を用いた新規化合物の合成に挑戦しました。仮説通りに進む実験ばかりではありませんが、想定外の化学反応から突破口が見つかることも。大学院では研究の応用にも挑戦し、社会に貢献したいです。
応用科学コース 研究室
有機材料研究室
二酸化炭素などを利用し、従来とは異なる材料からプラスチックや電池材料となる物質を合成しています。環境負担が少なく、社会に役立つ化学物質を作りだすことを目指しています。
環境と生体影響研究室
二酸化炭素などを利用し、従来とは異なる材料からプラスチックや電池材料となる物質を合成しています。環境負担が少なく、社会に役立つ化学物質を作りだすことを目指しています。
有機合成化学研究室
これまでに報告例のない全く新しい化合物を作っています。
色が変化する化合物や生物活性を示す化合物の合成を目標とし、これらが工学関連材料や医薬品の種となる研究を
行っています。
ファインセラミックス研究室
全元素が研究対象です。あらゆる元素の組み合わせとプロセスを変更することで、エネルギー分野に貢献する新たな機能を有したファインセラミックス材料を開発します。
高分子化学研究室
地球環境保全をめざした原料に石油を利用しない環境に優しいバイオマスポリマーの研究が急速に進展しています。グルコースや砂糖を出発原料とした新しい高性能ポリマーの開発を進めています。
資源エネルギーシステム研究室
化学物質と化学反応を上手に組み合わせて新しい機能を発揮できるシステムの開発について研究します。成果を気候変動などの地球環境問題の解決に活用します。
環境化学・環境生物研究室
優れた機能をもつ新物質を合成し、これを応用する研究や、自然界に生息する有能な生物の探索と評価等を進めています。これらの研究を通じて新しいことを発見する喜びや驚きの実体験が可能です。
